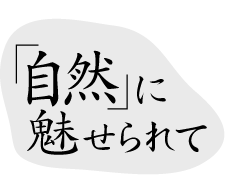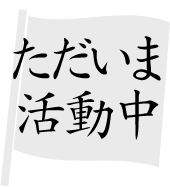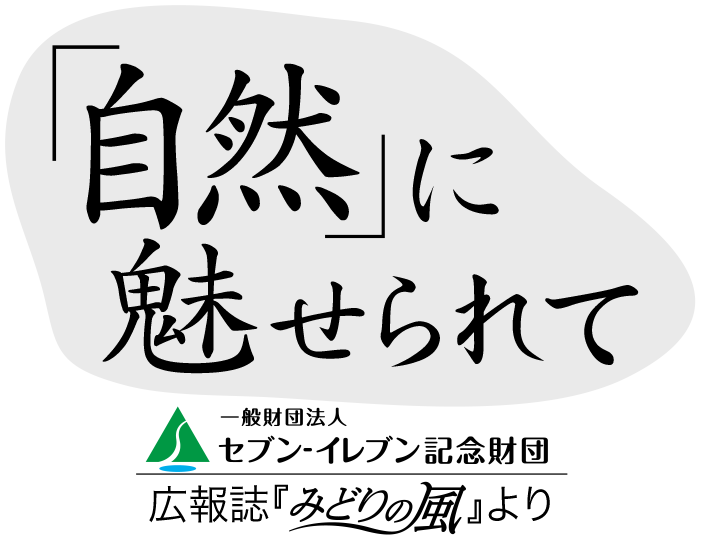
野生ラッコ
復活を見守る
岬の番人
片岡 義廣さん
(写真家、NPO法人 エトピリカ基金理事長)
北の海に棲む生き物を観察して40年、片岡義廣さんはきょうも岬に立つ。国内で一度は絶滅したものの蘇った海獣・ラッコの姿を追うために。

──野生のラッコの愛らしさに魅せられて、北海道浜中町の霧多布(きりたっぷ)岬を訪れる人が増えている。見られなくなって久しいラッコがこの地で復活したのだ。
岬に居を構える片岡さんは、厳しい環境で懸命に生きる彼らの姿を一番近くで見つめ続けてきた。
片岡ラッコの存在に、私が地元の誰よりも早く気がついたのは、ほぼ一年中、毎日この海を見ているからです。東京育ちですが、動物や野鳥が好きで、15歳の頃から年間80~90日は全国各地を観察して歩く生活を送っていました。1985年に家族で霧多布へ移住してきたのも、当時はここで繁殖していた憧れの海鳥エトピリカを見たかったからです。
じつはラッコの姿も、来た年の秋から目にしていました。海鳥の観察中にたまたま沖合を漂う個体を目撃したのですが、正直「すごいものを見たな」と。まさかラッコに会えるなんて思ってもみませんから。



──片岡さんが驚くのも無理はない。国内のラッコが絶滅したのは20世紀初頭である。いまでは生息していたことを知る人さえ少ない。
片岡おもに北太平洋に生息するラッコは、毛皮を取るための乱獲によって、一時は絶滅寸前まで激減しました。その後、保護が進んで、北方四島あたりで増えた個体が千島海流に沿って、ここまで来たのでしょう、生息域の南端にあたるのが、北海道・道東の太平洋側ですから。それから数年ごとに現れ、2012年からは毎年見るようになりましたが、定着はせず、すぐに姿を消してしまいました。
──片岡さんは、2010年からNPO法人エトピリカ基金を立ち上げ、霧多布周辺に残る希少な海鳥や海獣の調査に力を尽くしてきた。再び姿を見せ始めたラッコが気にならないはずがない。
片岡2016年のことです。どうやら3頭のラッコが岬に棲みついたらしい――海鳥の観察をしていてそんな感触がありました。そこで私たちは従来の海鳥の調査活動とあわせ、翌2017年から年間通してラッコも調査することにしました。当時、根室のモユルリ島にもラッコが棲み始めていましたが、無人の離島なので常時観察ができません。人間の生活圏に近く、陸上から一年中ラッコを定点観測できる場所は、国内では霧多布以外にない。だったら、記録に残しておこうと思ったのです。
まず調べなければならないのは、本当に一年中ここにいるかどうか。さらに性別や個体識別、エサの種類など、調査1年目は基本的な生態を把握するところから始めました。
──岬に着いたときはまだ幼かった3頭は調査によって、オス1頭、メス2頭と判明した。そして調査2年目から繁殖が始まり、メス2頭が交互に出産するようになった。
霧多布が新しい繁殖地として安定するかどうかは、子供を産み育てるメスしだいです。最初の2頭のほかに若いメスも何頭かやって来たのですが、なかなか定着しません。動物が分布を広げるのは大変なことなんですね。また、文献等にはよく「メス同士はグループで暮らす」と書かれていますが、観察してみると実際はかなり排他的で驚きました。それぞれが独立して子育てをするみたいです。たまたま嵐で流されてきたメスが、ここで出産したとき、もとからいたメスが近寄っていったら、ギャンと悲鳴が聞こえるくらい蹴っ飛ばされていましたから。


──どのくらい観察していれば、そんな貴重な瞬間に立ち会えるのか。何かコツはあるのか?
片岡いや、ただ繰り返し何回も見ているだけですよ。1回の観察時間はけっして長くありません。寒いし、歳ですし、体に障りますからね(笑)。よそから見に来た人はそのときしか見られないから粘るけれど、近くに住む私には地の利があって、いつでも見られるんだから、いなかったらすぐ諦めて、また時間を変えて何度でも見に行く。それが結果的に、動物の知られざる一面に触れられることになったのでは。

──もちろん、愛らしい姿や微笑ましい場面だけでなく、野生の厳しい現実を目にすることも多い。
生まれた子が1歳まで無事に育つ確率は25%といわれています。天敵のシャチはこの海にはめったに来ませんが、台風や冬の嵐、それにオスのラッコの脅威も大きい。他の動物にも見られるように、オスが、子育て中のメスの発情を促すために子供を傷つけるのです。育児期間はおよそ6カ月ですが、母親がなぜか本来の子別れの時期より早く、子供を手放してしまうこともあります。そうなると、子供が1頭で生きていくのは難しいでしょう。
ある日の朝、岬から「ミギャー」と大声が聞こえてきました。行ってみると、泣き叫ぶ子供のまわりに、母親の姿はすでにありませんでした。それが子別れ。あっけないものですよ。 現在、霧多布にはメスが全部で5頭います。最初の2頭とその娘が2頭、そこへ昨秋から新しい大人のメスが加わりました。徐々に増えているものの、彼女たちがこのまま棲み続けるかは予断を許しません。



──本来、希少種の生息地は公けにしないのが原則だ。しかし、片岡さんは貴重な調査結果を地元に還元し、ラッコとの共生に向けた環境づくりに活かそうとしている。
片岡霧多布は観光地なので、隠そうとしても隠しきれません。実際、ラッコ目当ての観光客やカメラマンも増えてきました。ただ、一部には好ましくない行為も見られたので、町とも相談し、ラッコを脅かさずに楽しんでもらうためのガイドラインを作成し、看板やリーフレットで呼びかけています。
さらに観光地であるだけでなく、漁業の町でもあるので、いまはまだそれほど問題になっていませんが、繁殖地として定着した場合、いずれウニ漁などとの軋(あつ)轢(れき)が深刻化しないとも限りません。漁業にとっては有害だけど、希少な生き物であり、また街を活気づける宝でもある。その辺りのバランスをどうとるか――私の調査結果が冷静な議論の材料になればと願っています。
──ラッコは愛くるしい動物だけれど、それだけでなく、彼らの自然界の中で果たす役割を知ってほしいと、片岡さんは訴える。
片岡ラッコの好物のウニは、じつはコンブなどの海草を食害します。だから、ラッコが減ると、海の底はウニだらけになってしまい、海の砂漠化が進行してしまうんです。実際、ラッコが絶滅した北米ではそうなりました。ラッコが戻ると海草の森が蘇るので、魚も増えるし、脱炭素にもつながる。ラッコは、豊かな海の生態系バランスを整えるキープレーヤーなのです。
「『自然』に魅せられてバックナンバー
こちらよりバックナンバーの一部をご確認いただけます。(2022年冬号までを掲載しています。)

皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。
アンケートには回答期限がございます。
予めご了承いただけますようお願い致します。
https://ws.formzu.net/dist/S50941006/

冊子での送付希望、定期送付のお申し込み、バックナンバー送付希望はこちらからお願いいたします(無料)。受付フォームに移動します。 在庫が無い場合もございますので、ご了承いただけますようお願い致します。
https://ws.formzu.net/dist/S75655804/